クスリの話
食前薬を食後に飲んだらダメなの?
お題)
糖尿病の薬を、漢方と一緒に飲んでいたら医師から叱られた、……とのリクエストがありました。
1.効果も副作用も血中濃度次第
薬をのみ忘れたからといって、次にのむときに2倍量のんではいけません。また、効き目が感じられないから多めにのむ、症状が軽いから半分だけのむ……というのもダメ。副作用の心配が大きくなったり、十分な効果が得られなかったりします。それはなぜなのでしょうか。
薬を飲むことで体内に吸収された薬は、血液とともに全身へと運ばれます。目的とする場所で効果を発揮するには、血液中に溶けている薬の量、つまり薬の血中濃度がカギを握っています。
薬をのむと、徐々にその薬の血中濃度が上がります。そして、血液が全身をめぐるうちに、薬の成分はやがて分解・排出されます。
薬の効き目が表れるのは、血中濃度が一定範囲内にあるときです。濃度が高くなり過ぎれば副作用が出てきますし、濃度が低ければ十分な効き目が得られません。
ですから決められた量を、決められたタイミングで飲みましょう。
2.速く広がり速く効く順番
以下の図のように、内服は一番ゆっくり体内に移行します。
注射薬は、内用薬のように消化管を経由することなく、からだの中に直接薬を入れられます。
一般に、最も速く薬が全身へと広がって速く効くのは血管(静脈)への注射です。
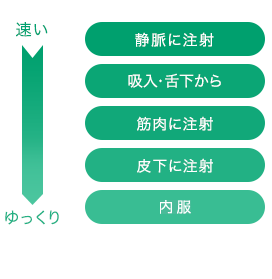
皮膚や粘膜から直接吸収される外用薬は、局所で効かせる、速く効かせる、持続的にからだに入れる……といった狙いがあります。たとえば、目薬やかゆみ止めの薬は、局所に効かせたい薬です。
速く効かせたい薬といえば、心臓発作のときに使う「ニトログリセリン」があります。この薬は、口からのんでも効果は得られません。
内用薬は、小腸で吸収されて肝臓に入りますが、ニトログリセリンは肝臓でほとんどが壊され、心臓まで届かないからです。そこでこの薬は、舌の下から粘膜を通して吸収させる舌下剤や口の中にスプレーする噴霧剤として使います。
持続的にからだに入れる薬には、禁煙補助薬として用いる「ニコチン」の貼付剤などがあります。時間をかけて、じわじわと吸収させます。
このように薬は、狙い通りのスピードでからだに広がるように作られています。
3.服用方法について(薬袋にある指示をカクニンする)
《食後》 「食後」とは、食事が終わってから30分以内。
内服薬の中で最も多い。食後30分というのは、胃の中で、薬が食べ物や胃酸の影響を最も受ける時間帯。空腹時に飲むと胃を荒らしてしまう成分が入っているかぜ薬や、食べ物と混ざることで吸収が良くなる薬などは、特に食後に飲むことが望ましい。
食後は、食べ物のおかげで配合成分が胃壁に触れにくくなるだけでなく、胃の蠕動運動(胃の内容物を腸に送り出そうとする動き)が活発であるため、有効成分が胃に留まっている時間が短くなり、より早く腸で吸収されると考えられている。
もし食後の薬を、食事をしていない状態で飲まなければならない場合、牛乳1杯でも、クッキー1枚でも口にしてから薬を飲むようにするとよい。
《食前》 「食前(しょくぜん)」とは、食事の20~30分前のこと。
胃の調子を整える食欲増進薬や、食べた後の吐(は)き気を事前に抑(おさ)えるくすりなどは、食前に飲むと効果がある。代表的な理由として、食物との相互作用や食物を吸収しようとする体の働きによって、薬の吸収が悪くなってしまう場合や、胃腸の薬のように食べ物を食べる前に薬を効かせて胃腸の働きを良くしておきたい場合などが知られている。
これらのケースは食べ物を口に入れる前に、ある程度薬を吸収させる(あるいは効かせる)必要があるので、薬を飲んだ後もしばらく何も食べない方が良い。口から薬を飲んだ場合、その薬が体に吸収されて効き始めるまでに大体30分かかるため、何か食べる前にそれくらいの時間は空けてほしいということ。それが「食前30分」の30分の意味。
漢方:食前または食間に。食後は、吸収が悪くなり、効果が半減する。その他、主治医の指示に従う。
《食直前》 食事と一緒に薬を用意して「いただきます」の直前に。
食事の直前に薬を飲めば、当然胃の中ですぐ後に食べたものと薬が混ざってしまう。つまり、「食前:食前30分」とは体の中で起きていることが全く違ってくる。
一番多いのは、血糖値をコントロールするための薬。食べた後に急激に上昇する血糖値をできるだけ押さえる目的。指示どおりに飲まないと、薬を飲む目的を達することができないばかりでなく、低血糖などの副作用が現れやすくなる。
《食間》 食事と次の食事の間、それも食後2時間ぐらい経(た)ってからのこと。
食べた物が消化され、胃の中の食べ物が少なくなる。空腹の時の方が、吸収が良い薬剤。
《就寝前》 文字どおり寝る前に飲む。
ただし、横になる直前に薬を飲むのはダメ。体が横になっていると、飲み込んだ薬が自然に胃から腸へ流れ出ていくことができにくいから。 薬が胃の中で溶けて吸収される前の状態で、食道の中や胃の中にとどまってしまうと、その部分に異常に「濃い」状態で薬が長時間接触していることになる。これは消化管の粘膜細胞にとって非常に良くない状態。食道や消化管の粘膜の表面が炎症を起こしたり、最悪は溶けて孔(穴)が空いてしまったりすることもある。
気をつけるべきポイントとして指摘される点を2つ。
まず良くいわれることだが、できるだけたくさんの水を飲むこと。薬が固形物のままで消化管にくっついてしまわないように、できるだけ早く水に溶かしてしまう。
次に、横になる(寝る)「10分から20分くらい前」に飲むようにする。
具合が悪くて床に伏せっているときでも、薬を飲むときだけは上半身を起こすか、その後トイレに立つなど工夫をして、体を起こした状態を作るのがよい。
《頓用(頓服)》 症状が出た時や出そうな時に、随時くすりを使う「頓服(とんぷく)」
4.食べ合わせなど避ける必要がある場合
《牛乳》
抗菌剤(抗生剤)の多く。薬剤の成分が牛乳のカルシウムと結合して、薬の吸収や作用を低下させる。つまり効果が落ちてしまう。
《グレープフルーツ・ジュース》
ある種の降圧剤(カルシウム拮抗剤、利用者は多い)、高コレステロール治療剤、睡眠導入剤のトリアゾラム(ハルシオン)、抗けいれん剤など。
グレープフルーツの果肉に含まれるある種の成分が、小腸上皮にある薬物代謝を阻害して、薬物の血中濃度を上昇させてしまう。結果として薬の効きすぎにより、血圧が下がったり、頭痛、めまいなどの症状を引き起こすことがある。
《納豆、クロレラ、緑黄色野菜》
抗血栓薬のワルファリン(ワーファリン)
《カフェイン》
抗うつ剤、抗けいれん剤、睡眠導入剤のゾピクロン(アモバン)、ゼンソクの薬、ある種の抗菌剤、アスピリン(濃度上昇)。
《光線》 多種の薬剤が当てはまる。 かならず、薬剤情報書の確認を!。
飲み薬やシップに複数あり。光線過敏症や、皮膚がんを誘発させる可能性のある薬剤。
- 実に多い! 抗菌薬、痛み止め、血圧降下薬(降圧剤)、糖尿病治療薬、添加物など
- シップ:モーラス(ケトプロフェン)類が代表。
食後、食前、食直前、食間など服薬タイミング
口から水と一緒に飲み込んだ薬は、食道を通過して胃に入り、そこで胃酸と混ざります。薬の配合成分は化学物質ですから、溶けだすと胃の粘膜などに何らかの刺激を与えます。
このとき、胃に食べ物が入っていると、薬が食べ物と混ざって胃壁に直接触れにくくなって胃への刺激を抑えることができます。
また、薬が食べ物と混ざると、腸で有効成分が吸収されるスピードが変化します。このため、薬によっては作用が現れやすくなったり、逆に現れにくくなったりします。
こうしたことから、薬を飲むタイミングは胃の中の環境を考慮して設定されています。





